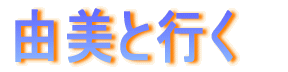|
29、
「出雲大社に近づいたよ」
「そうだ。出雲大社でお土産を買って帰りたいわ」
「私もお店に寄りたいな」
「ちょっと2人とも、来ていきなりお土産って。まず先にいろいろ見て、最後にお買い物ということにしようよ」
「それもそうね。とにかく土産物屋に寄ってくれるのならいいわ」
「じゃあ、日御碕から行くことにしよう」
恒之は、出雲大社の前を通り過ぎて、海岸沿いの道を北に向かった。
断崖絶壁が続く荒々しい海岸線を眺めながら、10分程走ると日御碕灯台が見えてきた。
駐車場に車を置き、少し歩くと灯台の下に着いた。
「大きいわね」
「上に人がいるよ。上がれるみたいだ」
「ねえ、上がってみようよ」
「そうするか」
入口で、わずかではあったが入場料を支払い、靴を履き替えた。
「大きく見えたけど、階段はかなり狭いわね」
人が1人通れる程度の巾だった。
時折、下ってくる人があり、踊り場で待って行き違った。
「上まで上がるのは大変みたいね」
「明日、足が痛くなるかもしれないよ」
ゆっくりではあるが、ほとんど真上に向かう急な螺旋階段だからかなりきつかった。
「お父さん、まだ着かないの」
「さあ、あとどれくらいあるのだろう」
そんな話をしているところに、小学生が降りてきた。
「162段あるよ」
「そんなにあるの」
「まだ半分上がったところよ」
小学生の言葉に、洵子と明代が驚いていた。
それでも、どうにか上まで上がり切った。
ドアが開けてあり、そこから外へ出ると周りが展望できるようになっていた。
「お母さん、怖い。凄い風が吹いているよ」
一旦は外へ出た明代だが、すぐに戻ってきた。
恒之も外へ出てみたが、まるでジェットコースターにでも乗っているようだった。
「本当だ。吹き飛ばされそうだ」
洵子も覗いていたが、とても出れそうになかった。
すると、そこに外から戻ってきた女性があった。
恒之は、よく外に出られたものだと感心した。
「こちら側は、大丈夫ですよ」
その女性が教えてくれた。
「そうですか」
明代は、早速外へ出て、先程とは反対側へ回った。
恒之と洵子も続いた。
「こちらは、風がきつくないわね」
「ああ、これなら全然okだよ」
「遠くまで良く見えるね」
3人は、灯台の西側から周囲をしばらく眺めていた。
恒之がふと見ると、近くの岩場に展望台が設置してあるのが見えた。
「ほら、海岸沿いに遊歩道や展望台があるよ。あのあたりからの景色も良いのかもしれないよ」
「そうね。行ってみましょうか」
「そうしよう」
また、螺旋階段を下った。
何組か上がってくる人たちとすれ違った。
「何処まで上がるのかしら」
「162段ありますよ」
明代が、階段の数をその人たちに教えていた。
「そんなにあるのか」
誰しも考えることは同じだった。
階段を降りきって下に着くと、皆ホッとした。
そして、そこから海岸へ続く遊歩道に向かった。
「ここから見る灯台は、とても素敵ね」
日御碕と記された石標のあたりから灯台を見ると、岩場にある松の木の背後に白く聳え立っていた。
恒之は、その荘厳とも思える灯台の姿を撮影しようとカメラを構えた。
「そこの展望台に行ってるね」
2人は、先に歩いていった。
恒之も灯台を数枚撮影して後を追った。
「ねえ、お父さん見て、あの島の上一面が鳥で一杯なのよ」
「おおっ、あれがウミネコの繁殖地の島だよ。本当に凄い数だなあ」
とても、数えられないほどのウミネコが、島の上にぎっしりと群れていた。
「5千羽いると書かれているわ。12月頃に飛来して、4~5月頃に産卵し、7月頃には、北の海へ飛び去っていくそうよ」
「渡り鳥なのね」
2人が表示板を見て話しているので、恒之も見た。
『経島とウミネコ』とあった。
その近くに、地図のある案内板も立っていた。
『御厳島(みいつくしま)?』
そこの地図には、経島が御厳島と記されていた。
恒之には、何か曰くがありそうに思えた。
「どうかしたの?」
恒之が、首をかしげているので、洵子が近づいてきた。
「あのウミネコの島は、御厳島と呼ばれているようなんだ」
「経島とも御厳島とも呼ばれているのね」
「厳島という名称は、須佐之男尊の娘の市杵嶋姫命から由来していると言われているから、この御厳島もきっと同じだろう」
「厳島って広島の?」
「そう。須佐之男尊が九州を制圧した時に、卑弥呼を妻にしているんだよ。ちょうど、出雲を制圧した時に稲田姫を妻にしたようなものかな。その卑弥呼との間に、市杵嶋姫命を含む3人の姉妹ができたそうだよ」
「須佐之男尊と卑弥呼との間に、3姉妹が?」
「それが、宗像3女神として奉られているんだよ。主には航海の神とされているよ。宮島にある厳島神社にもその3姉妹が奉られている。その中の一人が多紀理毘売命で、大国主命の御后として出雲大社にも奉られているよ」
「ということは、宮島のあたりは出雲勢力の拠点だったのかしら」
「おそらくそうだろう。さあ、戻ろうか」
「そうね。あら?」
その場を立ち去ろうとしていた洵子だったが、先ほどの地図を見てふと気になったようだ。
「ねえ、大海なんて言うかしら」
「大海?」
「ほら」
そこには、御厳島とある横に、日本海を表す名称として『大海』と記されていた。
「なるほど。やはり、大国の山で大山、そして大国の海で大海ということだよ」
「大国?」
「大国主の大国。大国というこの列島を制圧していた出雲王朝があったということだよ。そしてその国を、中国は邪馬臺(台)国と呼んだ」
「ふうん」
「邪悪な騎馬民族の大倭王がいる臺(台)ということかな」
「あまり好感は持たれていなかったみたいな名前ね」
「万里の長城を築いたくらいだから、中国が、鮮卑や匈奴などの北方騎馬民族に好感を持つことはあり得ないよ」
「そうね」
「その上、自らを日出る所の天子などと称する国書を隋に送るんだから、中国としては決して許せる国ではなかったんだろう」
恒之は、険しい岩場に波が砕け散っている荒々しい海岸を撮影しようとしたが止めた。この感動的な景色は、とてもカメラに入り切らないし、あるいは文字や言葉で表現できるようなものでもないと思った。
「この近くに日御碕神社があるけど、どうしようか」
「どちらでもいいわよ」
そう言いながら車を走らせた。
「お父さん、ほら、綺麗な建物が見えるよ」
「おおっ」
狭い谷間に鮮やかな朱色が映えて、まるで龍宮城を思わせるようだった。
「日御碕神社だ」
そこから少し道を下ったところに、権現造りの荘厳な神社があった。
階段を上がり境内に入ると、正面に拝殿があり、右手の階段をさらに上がったところにも社殿があった。
「上の本社と下の本社とあるみたいね」
洵子が境内に立てられている由緒書きを見ていた。
上の本社は、神の宮とも言われ須佐之男尊が奉られている。
そして、下の本社は、日沈(ひしずみ)の宮とも言われ天照大御神が奉られている。
「日沈宮は、千年前、村上天皇の頃にここに移ったとあるわ」
「元は、あのウミネコの御厳島にあったみたいだ。そうか、それでその名残で、あの島に鳥居が建てられているんだろう」
「祭りの時に、唯一宮司だけが島に渡ることができるとあったのは、ここに書かれている神幸祭の時かもしれないわね」
「だろうね。8月7日とあるから、ウミネコが、北の海に飛び去った後だよ。未だに聖域だということかな」
「神の宮は、2千5百年前にここに移ったとあるわよ。本当かしら」
「須佐之男尊は、3世紀頃だから、それはあり得ないだろう。あるいは、2千5百年前は、中国では春秋時代にあたり、当時、呉や越からこの列島にかなり人が流れてきているそうだから、須佐之男尊より前は、その人達を奉っていたのかもしれないよ」
「多くの人たちが大陸からやってきたんでしょうね」
「そういう人たちによってこの国は造られていったんだろう。また、紀元前3世紀頃、秦の始皇帝から逃れて、徐福が若い男女2千5百組を引き連れてやってきたという徐福伝説もあちこちに残されているよ」
「徐福?」
「徐の福かな。古事記で一番最初に現れた神が、天之御中主神と言うんだけど、この神が、実は徐福を意味しているのではないかという説もあるんだよ」
「本当かしら」
「出雲大社の本殿の神座は、西をむいているんだけど、その神座の前、つまり参拝者に対して正面にあたる場所に御客座5神が奉られているんだよ。古事記の中にも登場するその5神の中に天之御中主神がいるんだ」
「そうなの」
「その天之御中主神が、実は徐の福を意味しているのではないかと言われ、古事記は真福寺で見つかっている」
「ちょっと意味深ね」
「その真福寺では7福神のお祭りもあるそうだ。福が奉られているんだよ。7福神は船に乗っているだろう。徐福も船に乗ってやってきている。稲作など農耕や様々な技術をこの列島にもたらした、まさしく福の神だよ」
「面白そうな話ね」
「今となっては真偽を確かめるのは難しいだろうな」
恒之は、一段高い所に建つ上の本社である神の宮やその周辺を撮影した。
「神の宮は、まるで日沈み宮を見下ろすように建てられているのね」
「須佐之男尊が、天照大御神を見下ろしているようだ。出雲では、須佐之男尊が最高かつ最強の神だということだよ。出雲が藤原の勢力に征服されるまでは、全国の神社で最強の神として奉られていたんだろう」
「なるほどね」
「さあ、撮影も終えたから、今日一番行きたかった所へ行こうか」
「どこへ?」
「行ってみれば分かるよ」
「そう、楽しみね。どんな所かしら」
恒之は、また海岸線を南に下り、稲佐の浜を東に向かい出雲大社の西側にある小高い山を目指した。
「以前由美と来た時に、山の上に鳥居が見えていたので、気にはなっていたんだ」
「狭い道ね。大丈夫?」
車が一台やっと通れるほどで、対向車があったらどちらかがバックするしかない。
恒之は、車が下って来ないことを願いながら上を目指した。
その山の頂上まで上がったが、そこは狭くて、やはり車では上がるべき所ではないと分かった。
とりあえず、車一台は置けた。
「山の上は、ちょっと寒いわね」
明代が寒そうにしている。
車を降りると、かなり冷たい風が吹いていた。
そこには、それほど大きくはないが、見晴らしの良さそうな展望台があった。
3人は、その上に上がった。
「わあ、何てよく見えるの」
「ほら、お父さん、海の方にはウミネコがたくさん飛んでいるよ」
背後には半島の山々が迫り、右手には日本海がはるかに広がり、その波打ち際にはウミネコが群がっていた。
そして、対面には連綿とした中国山脈が見える。
「周囲には山々が、そして広大な日本海やそこに飛び交う鳥。もう少し気候の良い時期だと、もっと気持ちよく眺められるんだろうなあ」
「初夏の頃だと、それはもう素敵でしょうね。花もあちこちに咲いているかもしれないしね」
洵子も、結構気に入ったようだ。
「ここで今の自分達と同じように、この景色を眺めながら歌を詠んだ人がいたのかもしれないんだ」
「ええっ、何よいきなり。でも、ここに立てば、歌を詠もうと思っても不思議はないわね」
「そう思うかい。実は、万葉集の第2首は、ここで詠まれたのではないかと考えているんだよ」
「万葉集の歌がここで?」
「そう」
「誰が詠んだの?」
「大王だよ」
「大王って?」
「出雲大社の建っている場所にあった大国の宮殿にいた大王だよ」
「どういうこと、何と言っていいのか返事に困るわ。それで、どんな歌なの?」
恒之は、万葉集第2首の資料を洵子に渡した。
洵子は、それを手にすると、そこに書かれている歌を読んだ。
大和には 群山(むらやま)あれど とりよろふ 天の香具山 登り立ち 国見をすれば 国原は 煙立ち立つ 海原は 鴎(かまめ)立ち立つ うまし国ぞ 蜻蛉島(あきづしま) 大和の国は
「大和で天の香具山ということは、奈良県の香具山じゃないの」
「昨年、由美と奈良まで行ったけど、とてもこの歌が詠まれた場所とは思えなかったよ」
「そうなの」
「そもそも、奈良盆地には海もなければカモメもいないよ」
「まあ、そうね。それが、どうしてここなの?」
「蜻蛉島(あきづしま)とあるだろう。これは、島根半島を表していると思うんだ。つまり、蜻蛉島大和は、出雲を意味している。そして、出雲には7世紀頃まで大国つまり大倭国があり、大倭王が君臨していたんだよ。その王が、出雲大社の建っている場所にあった宮殿からこの山に登って国見をしたのではないかと考えているんだよ」
「たしかに日本海の広大な海原も見えるし、カモメと呼んでいたというウミネコもいるわ。繁殖地があるくらいだから当時もいたのかもしれないわね。でも、国原には煙立ち立つとあるけど、そんなにも煙が立っていたのかしら」
「生活のための煙もあっただろうが、出雲や対面する斐伊川の流域は、製鉄の一大産地だよ。たたら製鉄やその鉄を加工するためには火を燃やすだろう。向こうに見える山々にはその煙があちこちで立ち昇っていたんだよ。活気あふれる出雲王朝時代の歌が万葉集に残されたんだろう」
「でも、この山は奉納山と呼ばれているわよ」
「ほら、そこには鳥居と神社があるよ。直接的には、そういうことが書き記されてはいないけど、この山の山頂に鳥居と神社があるということは、この山頂は特別な場所だということだよ。そして名称も含め、藤原氏に征服された時に、国名や地名、歴史や文化などありとあらゆるものが藤原氏に奪われてしまったんだ。そして出雲王朝の存在を意味するものはすべて消し去られ、または、神話の世界へ追いやられてしまった」
「それは酷いんじゃない。ちゃんと歴史として残して欲しいわね」
「今でも、都合の悪い歴史は消されたり、都合良く変えられたりするくらいだから、千数百年前だと尚更だよ」
「でも、万葉集の歌が、奈良大和ではなく実は出雲で歌われていたということが、もし本当だとしたら凄いことよね。万葉の地は、実は出雲だったということになるのよ」
「それは、どうか分からないけど、出雲もその中に含められることにはなるだろう」
「『神話の国出雲』に、『万葉の地出雲』が加わるのね」
「万葉集で大王とか神について詠われている歌は多いから、それらは出雲王朝や出雲系の神を意味しているとは思うよ」
「ほら、お父さん、雪が降ってきたわ」
「雪?」
恒之が、明代の言葉に振り返ると、北側の山の斜面を雪が舞いながら、その雪の帯が西から東へ移動していくのが見えた。
「こんな神秘的な雪の降る光景を見るのは初めてだ」
「出雲は、何処か気候が他と違うように思えるわね。雲にしても、雪にしても、その景色に神がかり的な感じを受けるのよね。そう思って見るからかもしれないけどね」
洵子も雪の舞う光景に見とれていた。
「お父さん、午後は晴れると言ったのに雪が降ってきたじゃない」
「『お父さん気象台』の予報は、はずれたわね」
「出雲の神々が、すばらしい景色を見せてあげようと、演出してくれたんだよ。八百万の神に感謝しなければいけないよ」
「ええっ、お父さん、言い訳に神様を利用しちゃだめだよ」
「ねえ、ここも雪が降りだしたから、車に戻りましょうよ」
洵子の言葉で、3人は車に戻り、山を降りていった。
そして、出雲大社に参拝し、目当てのお土産も買い、神々の国出雲を後にした。
|