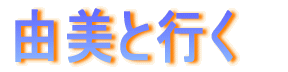|
27、
「最近、ようやく春めいてきたわね」
「そうだなあ。今年は、いつまでも雪が降って大変だったよ」
「明代も高校に入ると、ゆっくりできそうにないから、今の間に何処かへ出かけたいわね」
洵子が、恒之の横でいつものように旅行雑誌に見入っている。
「今の時期は、ちょっと忙しいよ。泊るのは難しいけど、日帰りくらいならいいよ」
「日帰りでいいわ。そんなに遠くに行きたいという訳でもないのよ」
そう言いながら、洵子は山陰を紹介する雑誌をめくっている。
「そうか、やっぱり『だいこく』と言っていたんだ」
「どうしたの?」
「先日、由美と、出雲にあったと思われる『だいこく』について話していたんだよ。でも、普通は『おおくにぬし(大国主)』と言っても『だいこく(大国)』という国があったとは思わないだろう」
「そうね。大国主命という神様のお話という程度で、大国があったかどうかまでは考えないわね」
「この前、由美と出雲大社に行ってきただろう。これは、その時に買った本なんだよ。その中に、大国を『だいこく』と読めるとあるんだ。ただし、『だいこく』という国があったとまでは書いてないけど」
「でも、大国という国があったからこそ、大国主がいるとも考えられなくもないわね」
「ここでは、『だいこく』とも読めるから、仏教の大黒天と習合させて考えられてきたというように書かれているよ」
「七福神の大黒様ね」
「七福神と言えば、恵比寿さんは、その大国主命の息子の事代主命だとも言われているよ。古事記の国譲りのところで、美保に出かけていたとあっただろう」
「そういえば、事代主命とあったわね。その神様が、恵比寿さんなの?」
「だから、美保神社は、全国に数多くある恵比寿神社の総本社なんだよ」
「そうだったの。それは、知らなかったわね」
「じゃあ、何処かに出かけたいのなら、天気の良い日に美保神社へ行ってみようか。近くに美保関灯台もあるよ」
「そうね。あら、ここにも書いてあるわ。美保神社は、全国に3385社あるゑびす社の総本社だって。祭神は、その事代主命と三穂津姫命だそうよ。三穂津姫命は、大国主命の御后なんだって」
洵子が、手元の雑誌を見ながら話している。
「となると、島根半島の西の端には出雲大社で大国主命が、東の端には美保神社でその后と事代主命が奉られているということになるよ」
「島根半島は、まるで大国主一族が両端を守っているみたいよね」
「出雲の国は、神様でいっぱいだよ。何と言っても全国に数ある神社のおよそ八割は、出雲の神様が奉ってあると言われているからなあ」
「そんなにも全国に出雲系の神社があるということは、この列島は出雲の国の勢力下にあったということなのかしら」
「おそらくね」
「でも、出雲と言えば神話の世界よね」
「そう、藤原平安朝に征服されて、神世の世界に追いやられてしまったのだろう」
「じゃあ、それまでは、出雲の勢力が全国にいたということなの?」
「この本にも、非大和の勢力は、大和の前に屈服したとあるよ。そして、非大和的なものは敗者だとも言っている。それだけでなく、それまで持っていた勢威も敗者の立場に置かれたら、その勢威の立場も逆転するとある。つまりスサノオ尊のことだろう」
「難しい話ね」
「ギリシャ神話も紹介されているよ」
「どうして、ギリシャ神話が?」
「プロメテウスって聞いたことがあるだろう」
「人間に火を与えてゼウスに罰せられた神よね」
「プロメテウスは、農耕や道具、放牧、そして言葉など多くのことを人間に教えた。そして、最期に火を使うことを教えようとしたのだが、ゼウスは『無知な人間に火を持たせてはいけない。強大になり、オリンポスを荒らしにやってくる』と言って許さなかった。そこで、プロメテウスは、ヘリオスの太陽の馬車から火を盗み出し、人間に与えた」
「人間にとっては、本当にありがたい神様だったのね」
「あらゆる産業の神だよ。ところが、ゼウスの怒りに触れ、プロメテウスは、罰としてコーカサスの山の岩に鎖でつながれ、はげ鷹に肝臓をついばまれ続けることになるんだ」
「こっそりと人間に火を与えたばっかりに、大変な目に会ってしまったのね」
「プロメテウスは不死身だから、腹を引き裂かれても、すぐに傷が治り身体はもとに戻る。そして、また引き裂かれるという、果てしのない苦痛に苦しめられることになった」
「あまりにも悲惨ね」
「最期は、ヘラクレスがはげ鷹を殺し、プロメテウスは、ようやくその苦痛から解き放たれた」
「たとえ、つくり話だとしても残酷よね」
「さて、このプロメテウスが、実はギリシャの先住民族の崇拝していた火の神だったそうなんだ。つまり、先住民族が征服されるとその神も敗者の地位に貶められてしまうというわけだよ」
「ということは、出雲に於ける最強の神であるスサノオ尊の立場も、逆転してしまったということなのね」
「そう。しかし、この本では、スサノオ自身もまた征服者であったとも述べているよ」
「えっ、どういうこと?」
「スサノオ尊が八岐の大蛇を退治する話は、先住民族の征服を意味しているということなんだろう。神社にある大きな注連縄は、蛇が連なっている姿が表されているそうだ。そして、志賀島で発見された金印の背には蛇が象られている。つまり、蛇は農耕民族にとっては、神聖な神だったのかもしれない」
「その神聖な蛇を奉る民族を、スサノオ尊が征服したということなのかしら」
「大蛇を切った時に、尻尾から剣が出てきたとあるけど、これはその民族にとっての象徴で、スサノオ尊による征服と彼らに対する支配を意味していたのだろう。だから、出雲の勢力が征服されると、その大蛇の剣も天照大御神に献上したことになってしまった」
「勝てば官軍、負ければ賊軍というようなことね」
「そうだな。敗者は、勝者の前にあっては、ひれ伏すことになってしまうのだろう」
恒之は、さらにその先を読み進めた。
「出雲大社の宮司により書かれた本だから、今まで知らなかったようなことばかりで、中々面白いよ」
恒之は、引き続きその本を読み進めていた。
「ねえ、松江城の近くの宍道湖の辺には、千鳥公園があるそうよ。あの宍道湖の夕日と千鳥、とても風情があるわね」
「宍道湖に千鳥がいるのかなあ」
「松江城のことを千鳥城とも言うそうよ。千鳥が羽を広げた姿に似ているから、そう言われているみたい」
「ふうん。ということは、以前は千鳥がいたんだろうなあ。千鳥は、干潟にやってくるそうだよ」
「今もいるかどうかまでは書いてないわね」
千鳥と聞いて、恒之にはちょっと気にかかるところがあったが、今は、本に書かれていることの方に興味を引かれた。
「出雲大社の神紋は、亀甲に有の文字なのか」
「神紋?」
「そう、家紋のようなものだよ」
「それが、亀甲に有なの。よく分からないわねえ」
「キッコーマンという会社があるのは知っているだろう」
「知っているわよ」
「その名前は、亀甲の中に萬という文字が入っているところからきているんだよ」
「ああ、あの六角形の商標ね。やっと分かったわ。その萬のところが有なのね」
「そう。ところが、出雲大社に行ってよく見かける神紋は、亀甲に剣花菱なんだよ。それは、出雲国造家の神紋だそうだ」
「剣花菱って?」
「×印のような剣の間の四ヶ所に花が入って、全体が菱形になっているんだよ」
「ふうん。で、それがどうしたの」
「出雲国造家の神紋と、出雲大社の神紋が違うということには、やはり何か意味がありそうだよ」
「どんな?」
「調べてみないと、まだよく分からないけど、有という文字は、十月を意味しているそうだ」
「有が十月を?」
「十と月を合体させると有になるだろう」
「あっ、本当ね」
「そして、十月といえば、神有月であり、神在祭だよ」
「なるほどね」
「神紋について、ちょっと調べてみる必要がありそうだ」
「あら、また調べることができてしまったわね」
「そうだよ。次々と出てくるよ」
「趣味とはいえ、大変ね」
恒之は、とりあえず出雲大社の本を読み終えることにした。
かなり、詳しく書かれているので読みごたえがあった。
「ねえ、出雲大社の近くに日御碕ってあるでしょう」
「あるよ。まだ行ったことはないけど」
「その近くにウミネコの繁殖地があるそうよ」
「ウミネコの?」
「島そのものが繁殖地になっていて、人は入れないそうよ」
「どうして?」
「年一回のお祭りの時に宮司が入るだけで、それ以外は禁足地になっているみたいよ」
「保護されているんだ」
「そこには元神社があったみたいね。今も鳥居だけは残されているようよ。写真も載っているけど結構大きな島みたいね」
「ちょっと見せてくれるかな」
「いいわよ」
恒之がその雑誌を見ると、小さな漁港のすぐ近くに島があり、その島一面にウミネコが群がっていた。
「経島(ふみじま)というのか、しかし、すごい数のウミネコだなあ」
「とても数え切れるような数ではなさそうね。でも、ウミネコとカモメとどう違うのかよく分からないのよね。猫のように鳴いていればウミネコなのかもしれないけど、じゃあ見た目がどう違うかと言われても全然見分けがつかないわね」
「ほら、だから、昔はカモメと呼んでいたとも書かれているよ。それにカモメ科の鳥だからカモメの一種なんだよ」
「そうなの。じゃあ、カモメでもいいじゃない」
「まあね。今の時代は、はっきり区別されているんだろうけど、区別しにくいのは確かだよなあ。あっ、じゃあ、あの稲佐の浜で見たカモメは、実はウミネコだったんだ」
「見たの?」
「出雲大社の近くにある浜に、それこそ数え切れないほどのカモメがいたんだよ。カモメだとその時は思ったんだけど、きっとここのウミネコが飛来してきていたんだ」
「すぐ近くだものね」
「でも、出雲大社や日御碕と同じくらいその島の歴史も古そうだから、ウミネコも相当古くからいたのかもしれないよ」
「そうね。古代の人たちも浜のウミネコを見ていたのかもしれないわね」
「きっと、カモメと呼んでいたんだと思うよ。ええっ、古代のカモメ!?」
恒之の脳裏に万葉集のあの歌が浮かんだ。
『カモメ。大王。蜻蛉嶋。夜麻登…』
「まさか…」
「どうかしたの?」
「そうか、あの山の上の鳥居だよ。なるほど、そういうことだったんだ。今度は、憶測や想像ではなさそうだ」
恒之は、この閃きが、果たして妥当かどうか考えていた。
『そうなると、その歌だけではなくなってくる。他の疑問に思っていた歌にまで波及していく。それに歴史すら変わってしまうことになる…』
あまりの内容がそこには潜んでいるので、恒之は身震いするような感動を覚えた。
「歴史とは、いったい何だろう」
「ねえ、何を考えているのよ」
「そうだ。行ってみよう。それしかない」
「何処に?」
「出雲にだよ」
「この前、由美と行ってきたんでしょう。また行くの」
「島根半島を東から西へと。行きたい。早く行きたいよ」
「何なのよ、急に」
「これは、すごいものが見れるかもしれないよ」
「なんだか知らないけど、近いうちに出かけましょうか」
「そうしよう。これは、楽しみだよ」
「私には、よく分からないけど、とにかくお出かけできるならいいわ」
恒之は、心が躍りだしそうなくらいワクワクしてきた。
『大王の見た景色が見れるかもしれない』
恒之は、改めて万葉集の奥深さを感じながら眠りについた。
|




邪馬台国発見
Copyright (C) 2008 みんなで古代史を考える会 All Rights Reserved.