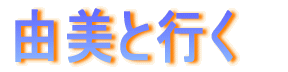|
21、
それから数日後だった。
恒之が朝起きると、空は雲に覆われていたが、青空もわずかに見えていた。
『これなら行けるかもしれない』
インターネットで天気概況をチェックしたが、出雲方面に雨雲は近づいていなかった。
『夕方からは分からないが、日中は大丈夫だろう』
先日ほどの快晴ではないが、撮影には問題なかった。
すぐに、出発の準備にかかった。
まずは、必須アイテムのパソコンとデジカメ。
そして、その撮影したデータを移すための接続コード。
あとは、オリジナルのお茶とおやつだ。
外で幾らでも、飲み物や食べ物は手に入るが、自前が一番である。
恒之は、10種類ほど茶葉が混ぜ合わされた物に、さらに数種類を加えて、3回煮出す。
すると、成分もよく出て、ちょうど良い濃さにもなり、とても美味しくなる。
胃腸にも良く、風邪もひかない。
恒之は、日頃より、『命の水』と言って、毎日欠かさず飲んでいる。
1度に3日分ほどできるから、そんなに手間もかからない。
出かける時は、そのお茶に蜂蜜を入れて、程好い甘さにする。
これに、ちょっとしたお菓子と果物があれば完璧である。
外出先での糖分と水分補給は、自分で用意するのが肝心だ。
朝食も済ませ、出発の用意ができた。
由美も準備ができたようだ。
「じゃあ、お母さん、行ってくるね」
「気をつけてね」
恒之と由美は、洵子が見送る中、出雲へ向けて出発した。
途中、反対車線で事故があったようで、大きなトラックが二台止まっていた。
完全に遮断されてはいなかったが、それでも長い渋滞になっていた。
「ちょうど通勤の時間なのに大変ね」
「八時前だから、きっと、皆あせっているよ」
しかし、どうすることもできず、ただ走り過ぎるしかなかった。
出雲大社には、2時間半ほどで着いた。
まだ寒い2月の平日とあって、駐車場に車はそんなに止まっていない。
それでも、観光バスで団体客が来ていた。
その駐車場から、すぐに拝殿に行けるので団体客は、そちらを通り抜けていた。
「そこじゃなくてこちらから行こうか」
2人は、松林のような参道を通って拝殿へ向かった。
その参道の両側には、大国主命の大きな像が建てられていた。
「こんなに人の少ない出雲大社の写真はそう撮れないよ」
恒之は、早速に拝殿やその背後にある本殿を撮影した。
「ねえ、お父さん。出雲大社の注連縄は、もっと大きくなかったかしら」
「確かにそうだよなあ」
「何かの写真で見たイメージでは、もう少し大きかったように思うのよね」
恒之は、全体の写真を取り終えたので、周辺をまわることにした。
「ちょっとこちらへおいで」
「どうしたの」
「出雲大社、謎体験だよ」
「謎体験って?」
「まず、その場所へ行ってみよう」
恒之は、本殿の真横にあたる場所に来た。
そこには、何か表示がされていた。
「そうか。隠された秘密でもないのか」
「何が?」
「ここに書いてあるから読んでごらん」
由美は、木の板に書かれている表示を読んだ。
「ええっ、本殿の中の神座は横を向いているの?」
「そうなんだよ。まさか、こうして表示がされているとは思ってもみなかったよ。驚いたなあ」
「お父さんは、表示がされていることに驚いているようだけど、私は、横を向いていること自体に驚いたわ。普通、本殿と同じように正面を向いているでしょう」
「そうだよなあ。ところが、この出雲大社では、本殿は南向きだが、神座は西を向いているんだよ」
「じゃあ参拝に来た人に対して、神様は横を向いていることになるじゃない」
「だから、こうやって横からも参拝が出来るようにしてあるのかな。こちらが、神座に対して正面ですよって。隠してないだけ良心的だよなあ」
「そういうのって良心的って言うのかしら。でも、どうして、そんなことになったんだろうね。ここには、本殿の間取りの関係でそうなったとあるけど、どうかしらね」
「出雲大社最大の謎だよ。まあ、次に行こうか」
恒之は、本殿の裏に廻った。
そこには、素鵞社(そがのやしろ)があった。
「ここは、須佐之男尊が奉られているのね」
「この社は、北側にある八雲山を背にして南を向いている。一番奥の真中から全てを見渡すように建っているんだ。そして、拝殿の真正面に相対している。つまり、本殿の神座は横を向いているから、参拝者は、本殿のさらに奥の須佐之男尊を拝んでいることになるんだよ」
「すごい仕掛けになっているのね」
「たまたまそうなっているだけで、特別な意味はありませんと言われてしまうかもしれないけどね。さあ、向こうにも行ってみようか」
2人は、神楽殿の前に来た。
「わあ、大きな注連縄ね。これよ、よく写真で見る出雲大社の注連縄だわ」
「そうだよ、こちらの注連縄だったんだ」
そこでは、出雲大社の発行する冊子が、いろいろ売られていたので、恒之は2種類の本を購入した。
そして、神楽殿の写真も撮影した。
「さて、朝が早かったから、そろそろ昼食休憩にしようか」
「そうね、出雲と云えば出雲蕎麦よね」
2人は、駐車場の近くに並んでいる蕎麦屋に入った。
「出雲蕎麦と云えば割子蕎麦だよ」
割子蕎麦とは、3段重ねの器にそれぞれ違った薬味が載せられていて、出雲名物となっている。
「でも、寒いから暖かい蕎麦も食べたいわね」
「そうだな。じゃあ、天婦羅蕎麦も1つ頼むか」
まだ、昼には少し早い時間だから、2人以外にお客はいなかった。
注文した品物が来るまでの間、恒之は、店内を見回していた。
ふと、壁に貼ってある写真に目がいった。
古事記の中には、出雲の祟りを恐れて、天皇が出雲の神を奉ったり参拝する話がある。
その写真には、数年前、出雲大社を参拝する明仁天皇と美智子皇后の姿があった。
「お父さん、ほら、この写真」
先ほど買った冊子にも同様の写真が綴じられていた。
「古事記の世界は、今もなお生き続けているよ」
「さあ、どうでしょうね。あら、大国主命の子どもである事代主命の娘は、媛踏鞴五十鈴媛命と五十鈴依媛命と言うそうよ」
「たたらとついているということは、やはり製鉄一族だったということかな。そう云えば、伊勢神宮の側に流れている川は、五十鈴川だったよ。何か関わりがあるのかもしれないなあ」
「媛踏鞴五十鈴媛命は神武天皇と、五十鈴依媛命は第2代天皇と結婚したことになっているわ」
「天皇家と出雲とは、今も婚姻関係があるそうだよ」
「ええっ、今も」
「それが、どういう繋がりでそうなっているかまでは、分からないけどね」
「ふうん、そうなんだ」
「あれっ、ちょっとそれ見せてくれるかい」
「いいわよ、どうかしたの」
恒之は、由美の持つ冊子を手にし、表紙の古絵図に見入った。
「これは、鎌倉時代の出雲大社周辺を描いたと言われる絵だそうだ」
「それが、どうしたの」
「見てごらん。出雲大社の周辺に草が茂っているように描かれているだろう」
恒之は、由美にその冊子を手渡した。
「そうね」
「それも、相当広範囲のようだ。それってどんな草に見える?」
「葦みたいよ」
「砂洲のような地域で、耕作地や宅地じゃなさそうだ。斐伊川や、島根半島側から流れ出てくる土砂で埋まったような場所だから、人の手がまだ入ってないように見える。洪水とかも多いから、人も近づけないのだろう」
「一面が、葦の原に描かれているわね」
「これは、葦原中国だよ」
「えっ?」
「古事記に出てきた葦原中国だよ」
「ここが?」
「何故、葦の原なんて書かれているんだろうと不思議だったんだよ。まさしく葦の原の中にあるよ。葦原中国と命名した理由はここにあったのかもしれない」
「どうかしら」
「それに、鹿もいるよ。たくさん描かれているだろう」
「そうね」
「島根半島には、鹿島という地名も残っているようだし、鹿島神社とか奈良公園の鹿とも何か関係があるのだろうか」
「さあ、何とも言えないわね」
「そうだよな。おっ、蕎麦が来たよ」
2人は、一旦歴史の話を置いて、本場出雲の蕎麦を堪能した。
そして、食べ終わり、ちょっとくつろいでいると、由美がまた先ほどの冊子を開いていた。
「ふーん、そうなんだ。天皇家からは、毎年5月14日に催される例祭に勅使が参加しているそうよ」
「毎年ねえ」
「かなり緊密な関係みたいね」
「そうだなあ。微妙な緊密関係だよな」
「昨年、初詣で行った熊野大社との亀太夫神事も載っているわよ」
「出雲大社の宮司が、熊野大社に火きり臼と火きり杵を受け取りに行く時の儀式だろう」
「そうよ。変わった儀式が残されているわね」
「熊野大社、つまり、須佐之男尊から神聖なる火を授かるということを意味しているのだろう。熊野大社は、日本火之出初之社とも言われていたようだからね」
「身逃神事(みにげのしんじ)という行事もあるそうよ」
「身逃神事?」
「8月14日の夜から15日の未明にかけて行なわれる神幸祭のことよ。出雲国造が夜自宅を出て、他の社家で仮宿した後、深夜3時頃に帰宅するそうよ」
「何だろう。身逃げと言うくらいだから、何かの危険から身を守るために、一時的に避難をしたということなのかな」
「ええっ、もしその途中で人にあったら、また大社に戻って再び出て行くんだって」
「そんなこと言ったって、用事があって出かける人もいるだろう」
「だから、その日の夜は門戸を閉じ、謹慎して戸外に出ないようにしているそうよ」
「ということは、周辺の皆さんも家の中で固唾を飲んで見守っているんだ。あるいは、決して見てはいけないということを意味しているのかも」
「変わった神事よね。あら、神在祭だって。やっぱり、出雲よね。他所では神無月だけど、ここでは、神有月なのね。旧暦の10月10日の夜に、稲佐の浜で全国の八百萬神々をお迎えする『神迎神事』があるんだって」
「稲佐の浜で?」
「そうみたいよ。それも夜中よ。その写真も載っているわ」
「ちょっと、見せてくれる」
「いいわよ」
そこには十数名の神官が、夜の浜で神迎えの神事をしている様子が写っていた。
そして、めくって神在祭のところを読むと、その翌日11日から17日まで神事が行なわれるとあった。
「どういうことなんだろう」
「どうしたの?」
「古くは、『神在ノ斎(いみ)』と呼ばれていて、周辺では、この期間、宮の掃除はしない、家屋の大工仕事はしない、土木工事はしない、遊興音楽はしない、そして、最も静粛に祭祀を奉じているとあるよ。だから、この祭りのことを『御忌(いみ)祭』と言うそうだ」
「何か、お祭りじゃないわね」
「変だよな。1年ぶりに全国から神様が集まるというのに、まるで喪にでも服しているように書いてあるよ」
「『御忌祭』と言うのも変よね」
「天照大御神が、天岩戸に隠れた時は、大騒ぎをしていた神々だよ。1年ぶりに再会するんだから、こんな時こそ、また大騒ぎをしたり、歓迎の祭典のようなことがあってもいいはずだろう」
「何があったのかしら」
「というか、何のために毎年集まるのかということだよ」
恒之は、その冊子を由美に渡して、しばらく考えていた。
その間に、続きを由美が読んでいる。
「ここから、西の方にある上宮(かみのみや)で、八百萬の神々が集まって神議をするそうよ。だから、この期間は、この上宮で神在祭が行なわれるんだって。仮宮とも言われているそうよ」
「大国主命のいる本殿でなくて、上宮に八百萬の神々が集まるって?」
「そうみたいよ」
「何か、分からないことばかりだよ。とにかく、そこへ行ってみよう」
「そうね、そうしましょう」
会計を済ませて玄関を出ると、その店のおかみさんがお客の呼び込みをしていた。
「すみません、稲佐の浜はこちらでしょうか」
ちょうど、人通りが途切れていたので尋ねてみた。
「はい、そちらを真っ直ぐに行かれたら海に出ます。坂を下ったすぐ右に、八百萬の神様がお集まりになる宮がありますから、お寄りになったらどうですか」
「そうですか、ありがとうございます」
2人は、言われた道を真っ直ぐ西へ向いて歩いた。
「やはり、さっきの神在祭は、周辺にしっかり根付いているようだ。一押しで勧めるくらいだから」
「そうみたいね。でも、海までは遠いようね。まだまだ海岸は見えてこないわよ」
「近くにあるように思ったんだけどなあ」
「まあ、歩くのも食後の運動にいいわよ」
「上宮が、何処にあるか探しながら行くとなると、やはり歩いていく方がいいかなと思ったんだが、結構距離があるようだ」
「お父さん、ほら」
「何?」
「出雲の阿国の墓だって」
「なるほど、ここにあったのか。ちょっとお参りして行こうか」
「今ちょうど、テレビでもやっているわね」
「そうだよなあ」
案内板も表示されていて、名所として整備もされていた。
道路の側を、少し上がった所にあった。
「周辺の墓石も新しそうだ。テレビの関係で、お参りに来る人が増えたからかな」
「有名になると大変ね」
他にもお参りに来ているグループもあったので、二人は、少し離れた所から拝んでおいた。
そこから、またしばらく歩いた。
「ほら、あんな所に鳥居が見えるわ」
「どこに?」
「右手に見えるあの山の上よ」
「本当だ。よく見えたなあ」
由美が言う方向を見ると、小さな鳥居が、小高い山の上に見えた。
「どうして山の上に鳥居なのかしら」
「さあ、何でだろうなあ」
「何があるのかしら。あそこまで歩いて上がるのはちょっと大変そうね」
「どちらにしても、今日は無理だよ」
「そうよね」
そして、そこから少し歩くと坂道を下った。」
すると、聞いていた通り右に折れる道があったので、そちらを入ると右手に社が見えた。
「きっとあれだよ」
「そうみたいね」
近くに行くと、出雲大社摂社上の宮(仮宮)と書かれていた。
「祭神は須佐之男尊とある」
「八百萬神も奉られているわよ」
「ということはだ。年に1回、全国の神々が、須佐之男尊の下に集合しているということだよ」
「何のために?」
「いったい何だろう」
「須佐之男尊を偲んでとか」
「それなら、熊野大社に集めればすむことだろう。何もここでしなくても」
「それも、そうね」
「そうか。きっと、そういうことだよ。由美、さっきの本を見せてくれるかい」
「いいわよ」
由美は、手提げのカバンから『出雲大社由緒略記』を出した。
「この表紙の絵が、大きなヒントになったよ」
「その絵がどうかしたの?」
「ここを見てごらん。これが、当時の稲佐の浜だよ。そして、その浜の北の端に神社が描かれているだろう」
「ちょっと読みにくいけど、仮宮とあるわ」
「稲佐の浜の南には家があるけど、北の仮宮のあたりは、何も無い砂浜だろう」
「そうね」
「つまり、建御雷之男神が、剣を突き立てて、大国主命に国譲りを迫ったのが、このあたりというわけだ」
「この上宮のあたりが、あの古事記の場面になるということ?」
「そう。そして、決して忘れないようにと仮宮が建てられたのかもしれない」
「でも、古事記で描かれたからと言って、神社まで建てるかしら」
「それが、ただの神話ではないとしたら」
「ええっ、じゃあ、あの話は実話だと言うの」
「もちろん、あの話の通りではないよ。むしろ実際は、もっと凄惨な殺戮があったのかもしれない。そして、古事記、あるいは日本の歴史で、最も大きな秘密はこの稲佐の浜にあると言ってもいいかもしれない」
「どういうこと?」
「つまり、この稲佐の浜では、建御雷之男神が大国主命に国譲りの話をしただけで終わってはいないということだよ」
「何があったというの?」
「おそらく、大国主命、つまり大国の主がこの稲佐の浜で殺されたんだよ」
「事代主命や建御名方命のように、あるいは、伊勢津彦のようにどこかへ逃げたのかもしれないわよ。その前に、大国主命は、出雲の国から出ないと言ったのだから、ここ出雲の国にずっと居たのかもしれないわ」
「少なくとも、どこかへ逃げたということはないだろう。子ども達を逃がすことはあっても、本人が、逃げるなんてことはないよ。分からないけど、そういう人だったと思える。きっと最後まで戦って、この稲佐の浜で最期を遂げたに違いないよ」
「そういうことが、本当にあったのかなあ」
「その命日、つまり殺されたのが、旧暦の10月10日の夜ということだよ」
「じゃあ、神在月で全国から神が集まるというのは、大国主命を偲んでということ?」
「まあ、あくまで憶測にすぎないけどね。でも、その神事の内容を見る限りでは、嬉しい再会とは到底思えないよ」
「確かに、喪に服すというか、葬式に集まっているみたいよね」
「だろう。そして、初七日が過ぎて帰っていくんだよ。つまり、大国主命の葬儀の事を今に伝えているんじゃないかな。その上で、毎年、大国主命の事を弔っているのかもしれないよ。やはり、本殿の中の神座が、西を向いているのは、これがその理由なのかもしれないよ」
「でもちょっと待って、大国主命って須佐之男尊の娘婿よね」
「そうだよ」
「じゃあ、この稲佐の浜で殺された大国主命が、その人?」
「そうではないよ。つまり、徳川将軍と言っても1人ではないだろう。だから、大国の主、つまりは王、大王だよ。多分、名前は別にあっただろうけどね。実際殺されたのは、その最期の大王、ラストエンペラーだよ。おそらく、出雲大社は、その大国の王宮の跡に建てられたと思えるんだ」
「王宮の跡地に出雲大社が?」
「数年前に、拝殿のあたりから、心御柱が見つかっただろう。あれは、その王宮のものかもしれない」
「先ほども、写真が拝殿前にあったわね」
「実は、お父さんは、その心御柱が発見された頃、たまたま出雲大社に来たんだよ。その時、まだ調査中だったから、その実物を見ているんだよ」
「ええっ、お父さん、出雲大社に来ていたの?」
「仕事の関係で、この近くにお見舞いに来ることがあって、折角だからと寄ったんだ。その時に、地面を2メートルほど掘ったあたりに、見えていたよ」
「へえ、そうなんだ」
「その頃は、歴史に興味を持っていたわけでもないから、古い物が発見されたんだなあというくらいにしか思っていなかったけどね」
「それが、以前の出雲大社の柱の跡だったと言われているのね」
「お父さんも、そうだろうと思っていたんだが、どうも変なんだよ」
「変って?」
「建て替えたのなら、そんなに中途半端に残さないだろう。それに、もし切ったのなら切り口が分かる。ところが、その柱は、そうなってはいなかった」
「どうなっていたの?」
「焼けた跡だよ」
「焼けた跡?」
「そう、木を焼くとあんな残り方をするよ。たとえば、火事の後の焼け残った柱は、あんな風に残るよ。ほら、この口絵の写真、どう見ても焼けた跡としか思えない表面だよ」
恒之が開いたところには、宇豆柱の写真があった。
「そうね、焼けたように見えるわね」
恒之は、ページをめくった。
「そして、こちらが心御柱の写真だよ。表面が、同じような状態だろう」
中のページにも写真が掲載されていた。
「ほら、『宇豆柱上面には焼土と共に』とも書かれているよ。間違いないよ」
「じゃあ、王宮が焼かれたということ?」
「おそらくね。そして、埋められて整地された跡に、出雲大社が来た」
「来たって、何処から?」
「昨年行った熊野大社で買った本には、出雲国造が意宇から今の杵築へ移った時期を、平安時代とも言っていたよ。790年代に国造にかかわる規則が作られていて、それより後のようだと書かれていた。ちょうど、桓武天皇の頃だよ」
「その頃に、出雲国造が移っているのね」
「おそらく、出雲大社も同じ頃に移っていると思われる」
「では、何処から移ったのかしら」
「上の宮と下の宮は、何処にでもある神社の形態だが、熊野大社には1社しかない。熊野山を隔てて東側にある山狭神社にも上山狭と下山狭が残されている。ということは、熊野大社にも上の宮と下の宮があったことは、容易に想像できるし、あったとも書かれている。熊野の字名にも上宮内と下宮内とあり、今の熊野大社は下宮内にあるよ。亀太夫神事は、その頃からの関係を伝えていると思える」
「ということは、熊野から移ったということかしら」
「きっとそうだろう。だから、出雲大社ができる以前、今の杵築には、大国の王宮があったということになる」
「大国ねえ」
「そう。代々の大国主命が大王として、そこにいたんだよ。そして、大王は殺され、証拠隠滅で王宮は焼かれてしまった。その大王の霊を弔うということで跡地に、出雲大社が建てられたのではなかろうか」
「そうなのかしら」
「古事記の元々は、その大国主命の祖先を伝える話だったのかもしれないよ。それを、藤原平安朝が、自分たちの話に造り替えたとも考えられる」
「お父さん、そろそろ行かない」
「そうだな。そうするか」
恒之は、上の宮の写真を撮り、そこを離れた。
「あれっ、こんなところにも祠があるよ」
「そうね」
「下の宮?」
「上の宮があれば、下の宮もあるということね」
「それにしても、こんな道端に建っているなんて変だなあ」
路地の片隅に、50センチ4方の小さな祠が建っていた。
「来る時にも通ったけど、気づかなかったわね」
「祭神は、天照大御神とあるよ」
「大御神は、皇室のご先祖神だとあるわ。それにしては、小さいわね。それも、路端によ」
「出雲の神は、なんと言っても須佐之男尊であり、大国主命だからね。出雲魂がここに現われているのかもね」
2人は、そこからすぐ側にある稲佐の浜に移動した。
「綺麗な砂浜ね。浜辺の真中に小島があるわ」
「ああ、あれは、力持ちの建御名方神が、手の上で転がしながら来たという古事記に出てくる岩だとされているよ」
「あの小島を手の上で?」
「まあ、お話だよ。ちょうど、その話にぴったりくる岩だからね」
「でも、さっきの話を聞いた後だから、浜がどことなく寂しそうに見えるわね」
「大国主命の、怨霊が漂っているのかもしれないよ。ほら由美、その後ろ!」
「ええっ、何?」
「大国主命の陰が!」
「もう、やめてよ」
「じゃあ、その大国主命を偲びながら、浜の写真を撮ってくるよ」
「どうぞ。私はここで待っているわ」
由美は、父に驚かされてちょっとご機嫌斜めだった。
だが、深夜、この砂浜に追いつめられて、大王や家臣が壮絶な最期を迎えたのかもしれないと思うと、恒之は、とても楽しい気持ちにはなれなかった。
やはり、10月10日の夜、ここで行なわれる神事は、その殺された人達の霊を弔うものだろうと恒之には思えた。
今、その稲佐の浜に人影は無く、多くのカモメ達が波打ち際に集まって鳴いていた。
|




邪馬台国発見
Copyright (C) 2008 みんなで古代史を考える会 All Rights Reserved.