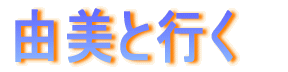|
17、
「おはよう」
「あら、今朝は早いのね」
恒之が、台所へ行くと洵子が朝食の用意をしていた。
「今日は、暖かそうだから、由美と一緒に遺跡を見に行こうと思ってるんだよ。由美はまだ寝てるのかなあ」
「遅くまで古事記の話をするんだもの。由美も疲れるわよ」
昨夜、由美が帰ってきた。
2月中はゆっくりできるが、3月に入ると、コーラス部の練習が始まるらしい。
入学式や新入生歓迎のレセプションのオープニングで歌うので、春休みといってもいろいろ準備があるみたいだ。
恒之は、自分のパンやコーヒーの用意ができたので食べ始めた。
「おはよう。あっ、お父さん、早いわね」
由美が起きてきた。
「おはよう。今日は天気がいいから、近くの遺跡を見に行こうと思うんだけど、一緒に行くかい」
「遺跡?」
「この近くにも、かなり貴重な遺跡があるんだよ」
「そう。じゃあ行ってみようかな。お母さんはどうするの?」
「私は、遠慮するわ。お留守番もいないといけないしね」
「そう」
そこに、明代もやってきた。
「おはよう。お姉ちゃん、早いね」
「お父さんが、今日、遺跡を見に行くそうだから、私も一緒に行ってくるね」
「へえ、すごいね。大学が休みで帰ってきたのに、まだ勉強みたいなことをするのね。お母さん、私、今日は倉吉へ買い物に行ってくるね」
「そう、気をつけてね。他のお友達は、これから高校受験で大変だというのに、あなたはお気楽でいいわね」
「私が一番初めに進学先が決まったのよ。今、みんな顔つきが真剣だから、何だか、私一人のんびりしちゃってごめんねえって感じだわ」
先日、学校から推薦してもらった高校へ明代の入学が決まった。
それで、本人も親も、とりあえずは、ほっとしているところだった。
「そうだ、倉吉へ行くなら、明代も一緒に乗せてもらったら」
「それいいな、お父さんいいかな」
「ああ、いいよ。どうせ同じような方向だから、構わないよ」
「良かった」
そして3人は、車で一緒に出かけた。
「お父さん、遺跡って、何処に行くの?」
明代が聞いてきた。
「東郷湖の周辺は、歴史的資料がたくさん出土しているんだよ。この国の歴史は、ある意味ここから始まったと言ってもいいかもしれない」
「本当に?」
「まあ、どこにも始まりはあるんだけど、ここが出発点と言えるかもしれないんだよ」
「ええっ、お父さん、そんなことある訳ないよ。こんな所で」
明代が驚いていた。
「自分の住んでいる近くに、そんな所があるなんて考えられないだろう」
「まず、あり得ないよ」
「どうして、そんなことが言えるんだ?」
「それは、私の台詞よ。そんなこと聞いたことないわ」
「だよなあ、おそらくこの周辺でそんなことを考えている人は、数少ないだろうな」
「数少ないなんてことないわ」
「とても、多いとは思えないよ」
「そうじゃなくて、誰もそんなこと考えていないということよ」
「そうかなあ」
「そんなこと言うと変な人に思われるよ」
車は、天神川を越えた。
「じゃあ、お父さん、倉吉駅の近くで降ろしてね」
「いいよ。で、また迎えに来るのかい」
「帰りは、自分で帰るからいいわ」
恒之は、明代を降ろし、由美と遺跡めぐりへと向かった。
「でも、明代が合格できて良かったね」
「本当だよ。行き先が無いようなことにでもなりはしないかと、それだけが心配だったよ」
「私も、ホッとしたわ」
「さあ、では、まずは馬の山へ行こうか」
「あの展望台のある所?」
「そう。かなり、見晴らしがいいよ。この周辺が一望できるんだ」
「展望台があるのは知っていても、中々、上がろうとは思わないよね」
「そうだよな。ところで、あの山を何故、馬の山と言うか分かるかい」
「さあ、知らないけど、きっと馬に関係するのかしらね」
「そう、実はあの山の上で馬を飼っていたんだよ」
「ええっ!」
「伯耆一宮の倭文(しとり)神社から、東郷湖周辺の荘園を書き記した地図が発見されてね。その山のあたりに、何頭もの馬の絵が描かれていたんだ」
「それで馬の山なのね」
「そのまんまだよな。ところが、これが大変なことを意味していたんだよ」
「どんな?」
車は、次第に馬の山の入口にやってきた。
そして、東郷湖から流れ出る橋津川の河口近くから、山の斜面を上がった。
「この山の上にいた馬は何処から来たのかということだよ。その頃、この周辺に馬がいたのかどうか」
「ということは、朝鮮半島から?」
「きっとね。匈奴や鮮卑など蒙古周辺にいた北方騎馬民族の一部がこの山にやって来たと考えられるんだ」
「ここに?」
「朝鮮半島の西側は、漢など中国の勢力圏内にあった。その勢力圏の外側を南下すると半島の東側を下ることになる。そして、半島の南東のあたり、後に、そのあたりに新羅国ができるんだけど、迎日湾から真東に向けて出港すると対馬海流に乗って隠岐島に着くことになる」
「そうなの」
「そこから、また海流に流されながら南下すると、ちょうどこのあたりにたどり着くんだよ」
「ふうん」
「伯耆は、元は波々岐(ははき)と言っていたそうだよ。その由来は、朝鮮半島から隠岐島まで一海(波)、そこからまた一海(波)来た岐、岐は港ということだよ。そういう説もある。この近くにある波々伎神社に、波々岐神が奉られているそうだ。橋津川から東郷湖に入ると穏やかな良い港だよ」
「そうね。でも、『ははき』と聞いたら母が来たという意味にも聞こえるわね」
「なるほどね。母も渡ってきたのかなあ。ここに来る途中、橋津川の河口の側に鳥居があっただろう」
「そう言えば、あったわね」
「彼らがたどり着いた歴史を伝えているんじゃないかな」
車は、頂上の展望台に着いた。
「わあ、見晴らしがいいわね」
周辺一帯が遠くまで見渡せた。
「天神川の河口に下水処理施設があるだろう」
「あそこに見えるわ」
「あの工事を始めた時に、砂を10メートルほど掘ったあたりから多くの遺構や遺物が発見されたんだ」
「あんな砂浜でねえ」
「それが、もう、出ない物は無いと言うほど、あらゆる種類の膨大な数だったので大きなニュースにもなるし、かなり長期にわたって調査もされたそうだよ」
「それは、すごいね」
「そこからは、およそ20メートル4方もあるような、巨大な高床式の建物の跡も見つかっているんだよ」
「ええっ、そんな大きな跡が?」
「その4隅には、直径2メートルを超えるような柱の跡も残っていたそうだ」
「そうなると相当大きな建物ね」
「かなりの高さの物見櫓だったのではないかということだ。おそらく、周辺の見張りや信号のやりとり、そして海の方からの攻撃を警戒する役割が大きかったかもしれないよ」
「見張り台ね」
「あるいは朝鮮半島からの来訪者の、灯台としての役割もあったのかもしれない」
「なるほどね。それが一番の役割かもね」
2人は、北の海岸方向を見ていたが、南の方にも回った。
「ほら、そのなだらかな丘陵で馬が飼われていたんだよ。近くには、その飼育をしていたと言われる人たちの集落も残っているよ」
「でも、本当に馬を飼っていたのかしら」
「さっき、荘園の図面が出てきたと言っただろう。馬の絵だけでなく、その荘園の所有者を示す中には、『馬野』という名前もあったんだ。その人が飼っていたかどうかは分からないが、この山で馬が飼われていたのは間違いないだろう」
「ということは、相当たくさん飼っていたのね」
「だろうなあ。飼う人の集落ができたくらいだから」
「そんなにたくさんの馬をどうしたのかしらね」
「さあ、騎馬民族だからいろいろ必要だったんだろうなあ」
2人には、馬をどう利用したのかまでは、分かりようもなかった。
「東郷湖もよく見えるね」
「先ほどの、長瀬高浜遺跡からは、ある目を引く遺物が発見されているんだ」
「何が?」
「小型銅鐸だよ」
「小型銅鐸?」
「そう、10センチ程の小さな銅鐸だよ」
「銅鐸って50センチくらいはあると思っていたんだけど」
「大きな物は、1メートル程の物もある。ところが、ここからはそんな小さな銅鐸が出土しているんだ」
「それが、何か意味しているの?」
「ほら、手前の湖畔に集落が見えるだろう」
由美は、東郷湖周辺に目をやった。
「見えるわよ」
「あの辺一帯には、祖先を奉る墓が無いんだよ」
「ええっ、どうして?」
「それは、あの東郷湖によるものだったんだよ」
「東郷湖がどうしたの」
「あの湖の底からは、温泉が湧いているんだ。だから、『東郷温泉』、『羽合温泉』と今でもあるけど、これは遠く古代から沸いていたんだよ」
「歴史が古いのね」
「だから、周辺の人々には、そんな温泉を湧き出す水神の国が、湖の底に存在すると思われていたそうなんだ。つまり、湯湖の国、黄泉の国だよ」
「ふうん」
「だから、人は亡くなったら、その湖底にある水神の国に葬られた。つまり、水葬だったそうだ。だから、地上に墓は存在しないんだ。もちろん、今はそんなことはしないよ。京都のお寺に納骨されているそうだ」
「なるほどね」
「そして、死者を葬る時、神のいる所まで誰が導くのか。それは、湖にいる魚なんだ。つまり、魚が水神の使者だったんだよ」
「神聖なる魚ね」
「そう、だからその儀式の時に、水の中であるものを叩いて、魚へ音の合図を送るわけだよ」
「何を叩いたの?」
「水の中で叩いて音がするものと言えば石だよ。魚の形をした石を叩いて、神の使いに合図を送った。それに使われていた石が、今も残されているよ」
「今にまで?」
「そう、とってもいい音がするらしいよ。チンチンとね。その石は、この馬の山で採れるサヌカイトと言われる石だそうだ」
「ちょうど、いい石があったのね」
「こうして、昔は、水神さんと言って、水の神を崇拝していたということだ。それは、稲作には水が大きな役割を果たしていたことにもよるんだろうけどね」
「水あっての稲作だものね」
由美は、東郷湖周辺を眺めながら、稲作をしていた人たちに思いを馳せていた。
「さて、そこに、北方騎馬民族が現われるんだ」
「えっ?」
「橋津川河口から上陸し、山頂で馬に乗った集団が現われたとしたら、どう思う?」
「そりゃもう驚くよね。見たこともない馬に乗って、すごい出で立ちで現われたとしたら、神様が天から降りてきたのかっていうくらいの驚きかな」
「そして、その馬には、きらびやかな織物や馬齢が装飾されていてご覧よ。この世のものとは思えないだろう」
「ものすごいカルチャーショックだったんだろうね」
「実際がどうだったかなんて分からないけど、なんか想像しちゃうだろう」
「そうよね」
「そして、少しずつ交流が進んでいくと、今まで見たことも無い彼らの文化に、次第に羨望の眼差しが送られるようになる」
「なるほどね」
「近くにある倭文織りという織物も、彼らによって伝えられたのかもしれないよ。そして、騎馬民族だから、鉄が必須だろう。今まで無かった鉄の農工具などが、周辺の農耕民族に、もたらされるようになる。それによって、農作物が豊富になってくると、農業のできない騎馬民族には、その収穫した作物が手に入ることになる」
「お互いの利益になったわけね」
「そういう中で、儀式に石を鳴らしていた彼らは、馬につけられている馬鈴を見て、とってもいい音がするのに気づくわけだよ」
「シャンシャンといい音色がするわよね」
「それって、石よりいいよなあということになり、多少、魚の形に変えて儀式に使うようになった。だから、銅鐸には、『ひれ』と呼ばれる部分があるんだよ」
「それが、小型銅鐸?」
「そう。初期の頃の物がここにあった、というかここから銅鐸の歴史は始まったのかもしれない。銅鐸が発見された分布図を、よく見ると、ここから広まったと考えられなくもないよ」
「本当かしら。もし、そうだとしたらすごいことよね」
「当初は、小さかったが次第に大きくなっていった。しかし、ある時期で銅鐸は消えるんだよ」
「どうしてかしら」
「だが、それは別の物に形を変えて残っているよ」
「どこに?」
「お寺で鐘を突くだろう」
「銅鐸が、梵鐘になった? 本当かしら」
「水中では石だが、地上では木を叩いていた。その木が木魚となったんだよ。お坊さんが、お経を上げる時に、木魚や鐘を叩いているだろう。仏壇の前には、小さい鐘が置いてあるだろう。みな、水神さんを祭っていた歴史がそこに残されているわけだよ」
「さあ、どうかしらね。話としては面白いわね」
「じゃあ、その小型銅鐸を見に行こうか」
「見れるの」
「ああ、歴史民族資料館に展示してあるそうだよ」
「それは、見たいわね」
「銅鐸の始まりとなった物がこの目で見れるんだから、感動ものだよ」
「早く行きましょう」
由美は、さっさと車に乗った。
資料館に着いたが、閉まっていた。
隣接の役場で聞くと、すぐに開けてくれたが、常時は開いていないのだろうか。
その担当の職員は、長瀬高浜遺跡の発掘当時のことなどを詳しく説明してくれた。
高床式の大きな建物跡が発見された時のことなども話していた。
「これだよ」
「本当だわ。小さいけど、でも銅鐸よね」
「ほう、これを儀式の時に鳴らしていたんだよ」
2人は、10センチもない銅鐸に見入った。
「この小さい銅鐸は、非常に珍しい物だと言われています」
その職員も説明してくれたが、詳しいことはよく分かっていないと言っていた。
その展示室には、家型埴輪、甲冑型埴輪、土師器、鉄製の農工具、釣針、銅剣など数多くの展示物が並べてあった。
周辺の古墳についても描かれていたが、かなり大きな前方後円墳が数多く発見されているようだ。
その中には、全長が100メートルを超えるような山陰で最大級のものもある。
「こちらの長瀬高浜遺跡では、弥生時代の遺跡で発掘されるような物が、殆ど出てきました。その多さには、本当に驚きました。かなり、長期にわたって、あの場所で生活していたと思われます」
その職員が言うように、本当に多くの種類の出土品が並べてある。
2人は、それらを見た後、いくつか資料をもらって、帰路についた。
「私たちの近くにも、貴重な遺跡があったのね」
「驚くよな」
「あの山に、朝鮮半島から北方騎馬民族がやってきたなんて、考えてもみなかったわ」
「ただ、あそこは終着点ではなく玄関口だったと思われるよ」
「玄関口?」
「そう、そこから天神川を上り、蒜山を越えて吉備に至った。そして、さらに南下して讃岐にまで達していると考えられる。また、西へ向かう集団もあっただろう」
「じゃあ、ここは上陸地点であり、中継地点だったということ?」
「そう、スサノオ一族もここを通っていったのかもしれないよ。河口の鳥居は、あるいはスサノオが、そこに降り立ったことを意味しているのかもしれない」
「それは、どうでしょうね」
「昨夜も話したけど、スサノオは、古事記で、元々出雲の生まれではなく、他所からやってきたように描かれていただろう。日本書紀には、高天原を追放になった時、一旦新羅に降り、そこから出雲に至ったとも書かれているよ。朝鮮半島の南東部、迎日湾のあたりは、新羅国だったから、そこを経てやってきたということかな。スサノオの頃に新羅国はまだ無いが、そういう経路でやって来たんだろう。そうだ、古事記の中で、新羅が御馬飼いにされていたんだよ。騎馬民族の国だと言いたかったのかもしれないよ」
「ということは、あの高い物見櫓が、本当に灯台というか、それを目印にやってきていたのかしら」
「朝鮮半島からやってきた人たちは、そこから、また西や南に移動していった。あるいは、奈良大和方面にも向かったのかもしれない。そんな歴史が見えてくるよ。温泉につかったのかどうかまでは分からないけどね」
「まあ、少しくらい休んで、いろいろ情報を聞いたりしたんだろうね」
「おそらくね。きっと、ここからまっすぐ南下した勢力が、吉備でたたら製鉄を築いたんだろう。あっ、馬だよ。そのために馬が必要だったんだ」
「馬が?」
「ここから、中国山脈を越えて行くんだよ。荷物もあるだろうし、大変な道のりだ。そのためにここで馬を飼っていたんだよ」
「なるほどね。旅行先の駅前レンタカーのようなものね」
「相当多くの人たちがやって来ていたのかもしれないよ。波々とね。あるいは、波々岐という地名には、波のように人がやってきたという意味も含まれるのかな。きっと、この周辺には、馬を提供するだけでなく、道案内や宿泊施設、あるいは航海を先導する人たちなど、渡航に関わる多くの人たちがいたのかもしれないよ」
「大陸からの、玄関口だったのね」
2人は、遠い過去を振り返りながら、家路についた。
「じゃあ、妻木晩田遺跡なんかもここを経て行った人たちなのかしら」
「どうだろう。あるいは、そうかもしれないよ」
「一度行って見たいわね」
「まだ早いから今からでも行けるよ」
「今から?」
「そうだ。あの近くに美味しい蕎麦屋さんがあるから、そこでお昼にしよう」
2人は、国道九号線を西へ向かった。
|




邪馬台国発見
Copyright (C) 2008 みんなで古代史を考える会 All Rights Reserved.